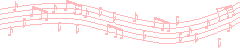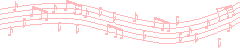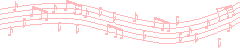
月刊 未詳24
2009年9月第30号 


2024年04月25日(木)17:31
[次ページ]
投稿する
ページ[ 1/6 ]
降り来る言葉 XLIII
木立 悟
荒んだ目の子が
昼を見ている
風は高い
指は遠い
地にあおむけの空が
上目づかいで地を見つめる
腕ひろげ
見つめる
誰かが見たいと望んだ数だけ
月は道に並んでいる
坂のむこう
街はまぶしく眠っている
救われはしない
進むひとひら
雨のなかを
水のなかを
己れの内外
揺らぎ濃淡
丘の上の
影と一輪
何もつまびくことなく
響きの上に置かれる指
培うことの無さ
光の粒にまみれて
番号は番号の終わりに向かい
くちばしは横からそっと押される
水のそばの列
ひかりぬるやか
ずっと知らないひとでいました
すれちがう数が両指のうちは
ずっと知らないままでよかった
こんなにこんなに苦しいのなら
空の牙の並びの内を
午後はすり抜け 落ちてくる
捨てられた鏡の胸をあけ
名づけたばかりのけだものを呼ぶ
光の種になっている
まだ半分しか呑みこめない
光の種になってゆく
人見知りする 眠りのかたちになってゆく
持つものも持たざるものも満ち足りて
ではかなわぬ願いの居るべき場所は
その答えは無いのです
どこまでもどこまでも無いのです
時がひたすら乱れて映り
どこかがどこかに似てはさまよい
曇を重ね敷きつめて
ひとりひとりの曇へと至る
穏やかなふるえ
まちがいの樹のはざま
喉知らぬあつまり
指と陽のまま
水飴に消える朝昼夜
幾度名前を呼んだだろう
昼はことさら巨きく撓み
まなざしを遠くへ遠くへ馳せさせる
[編集]
水引草
丘 光平
菜を切る
菜を切る、
とんとんとんと耳を澄ませて はたしてそれは
実に悲しいことではないのか
午後
手折られた庭で
水引草の ちいさな赤い思い出を
わたしらが追いかけた
水引草の
空は秋 あれらは
その高さに堪えきれないのだろう
ことりたちは
まばたきをすることもなく ひかりの粒を
頬張っている
[編集]
混濁する変質のミックス、鼓膜を欠く蛇の剥き身からの血液の模様
ホロウ
精神の欠片の中に迷い込んだ羽虫が悪いものを喰って死んだ、そいつの死骸がだんだんと腐って嫌な臭いをそこらに立ち上らせ…朝を二度迎えた後でなにもなかったみたいにそれは消えた
臭いの終わった死体は静かに、体躯を分解され、7日目の夜に忘れたように消えた、だけど流れた体液がその場に洩れたインクのようなしみを作って…渇いた血のように突っ張った痛みが長く続いた
眠り、という概念が冗談みたいに思えるような幾日かが過ぎ去ったあとで、あまり歓迎できない光が目の端にちらつくのを見ていた祝日、てのひらは微弱な電流に触れたように短く震え…まるであてのない思念のように
洗面台の端に両手を乗せて焦点の合わない目の奥を覗き込んでいたのはあれは昨日の話だっただろうか?オーバーヘッドプロジェクターのスライドする画面みたいな無機質な記憶、最も信じられないのはいつだって自分自身だった
途切れ途切れに見た夢の断片を繋ぎ合せてひとつの辻褄を合わせようとした、嘘なんだと呟きながら…そのあとに見えるものがどんな形かなんてそんなことはどうでもよかったんだ
見えたものは嘘だ、見えたものなんて全て嘘だ、最も信じられないのはいつだって自分自身だった、オーケストラが突然調和を乱すみたいにブレる感情の波をどんなふうに語ればいい、そしてそれは誰かに伝わることなどないのだ
正体!正体などあるわけがないのだ、虚けたようにただひたすら感情の波形を記録して変換してゆくものになど…風が強くなったな、おい、ひどく吹いているなぁ、あまりの勢いに首が根元からもげそうだ
枯れるにはまだ早い、全てのものが枯れ落ちてゆくには…なんといううんざりするような地熱だ、深酒の後みたいないびつな汗が身体の奥から滲み出してくる、晩夏―古い音楽のようにところどころ途切れがちな、晩夏
俺は口をつぐんでいたのだ、虫のように、静かに手をこする蠅のように、ぼんやりと…湿気と冷たい風がかわるがわるに訪れる季節に赤子の涎のようなネバつきを脳裏に感じながら
のたうちながらまぐわう蛇の記憶、こんな季節には必ずあの景色が記憶の表層をうろつく、あれを見たのはいつぐらいのことだったか…もういない人間がたくさんいた、あそこには、あの場所には
艶めかしい光を放つあの皮を剥ぐんだ、あれはいつか太陽に不気味な色を添えるためのフィルムのように思える、剥いで、血で、血で、血で、血で染めろ、ああは、剥き出しの肉片からゆっくりと流れる赤い血は、まるでそいつの存在がただの血管であると語るかのようだ
ホゥリィ・エンド、耳にしていたのはいつも予感だったんだ、それ以上、どんな形にも変質することのない…硬直した鼓膜に先端数ミリのドライバーで致命的な傷をつけてやれ、そうすることで画像に変換出来ないものが増えるから
落としてゆく、お前は落としてゆく、それ以上、どんな形にも変質することのない幾つかの血小板を…それはお前の本質的な欠陥だ、落としたものは拾い上げることが出来ない、なぜならそれにはもう違う組織がこびりついているからだ
本質的な欠陥、偏執的な本質、技巧的な欺瞞を懐に忍ばせながらすりガラスを伸びた爪の先で擦り続けるような音を聞いていた、梅雨時の雨音を退屈しのぎに数えているみたいな調子で
変質した、もののことを確かにそれと感じることが出来るか?たとえばそれが手の中におさまるものでくらいのものだったとして、何かが…形態や、目方や、質感が、変質した、そのさまを感じることが出来るだろうか、なぜそれを見ている、いつか放りだされた手紙のような文節を…
正体、本質、真実、真理―なぜそんなものについて知りたがる?変質こそがあらゆるものを正しく言い表すたったひとつの言葉だというのに…この身体が有機物である以上、断定出来る事柄などありはしないのだ、その認識こそが俺を生かせているすべてだ
落ちるように新しい音が、生まれる、生まれる、生まれる、生まれる…インプロビゼイションの度が過ぎるエンドの領域の痴呆、眼球が裏返ると見るまいとしたものの姿が垣間見える
ムービー・ショーの後でまっぷたつに裂けた犬を見たのはいつのことだったか、あの時のメノウのような大柄な犬の目つき、それが目にしたのはきっと終わりではなかったはずだ―あらゆるものを見て、そして忘れてしまったのだ、忘却だ、おそらくは極上の…
オーケストラ!オーケストラ、譜面通りの進行など投げ出してしまえよ!そうすれば拒絶の数が減るんだ、そのことが判らないのか、そのことが判らないのか、お前達には…乱れたリズムに泣くことがお前たちの命題ではなかったはずだろう
長くあとに残す、うんざりするようなフレーズがいつまで経っても終わることがなくて、俺はドライバーを握る手に力を込め過ぎて致命的なまで欠陥を鼓膜に残してしまう、上出来だ、上手くやったぜ…それはそう言ってごまかすことだって出来るのだ
[編集]
遠い鈴
木立 悟
光が花をまね
朝になる
一房一房が
波を追う
雨
丘を昇る霧
向かい合う手
結晶
くちびるの色を
手鏡に塗り
歯は透る雷
透る雷
引き出しのなかに
輝くことのないうたがあり
白と黒の水を湛えている
うすむらさきの砂が
何ものかの脳のように
荒地と荒地をつないでいる
はずんでいる
見えない傷に触れ
はずんでいる
枝の先に空は無く
ただ風と無がそのままに
ただそのままの径を描く
藍が溝につもり
黒よりも黒くなる
朝は低く
ささやきは遠い
三つの歩幅に重なる響き
誰もいないまぶしさの街
轍と轍のはざまを揺らす
[編集]
shine
いかいか
くるか、のせなかを
にわのためにひらいて、
わたしたちの、かなしい、
おうこくに、セーターを
あさはやくほして、
かえってこないくつしたの
ためのうたをうたい、
とおくでねむる、
かぜのおうのために、
わたしはけっこんする、
はだしは、けっして、
つめたくはないと、
くちびるがおしえて、
それをあしでなぞる、
うでは、ゆっくりと、
からだをもちあげて、
ちかいばしょから、
ばたばたとたおれるようにして、
ぬれていく
ふゆに、ことばをおぼえる、
と、おもいだして、
はじめからまたやりなおして
長唄のひとつでも、と、
京都の娼婦たちが、
騒ぎ立て、本能寺で、
燃え落ちるのが早いのは、
織田信長か、貴方の、どちらでしょうかねぇ、
と、くだらないことを本当に聞いてくるので、
うんざりしつつ、
その女の、作られた髪をとくようにして、
顔面を殴る、
変形していく、彼女の顔が膨らみ、
ぷっくらと、風船のように、
空でも飛べるようになると、
「あんさん、こどもを作った女の
腹もこないなようにふくれるんですわ」と笑う
たしかにそうだなぁ、と異様に重みを持った、
女の顔をじっくりと眺める、
織田信長はんも、きっとこないなようにして、
大阪湾に死体をいっぱい浮かべなさった、
水を吸ってパンパンに膨らんだ、男たちの、
上をあの人は、それでも燃え落ちながら
すすんでいったんですわ、と、
うるせぇ、京都弁なんて緒戦、花街言葉で、
ホステスの接客用語みてーなもんだろうが、
舞妓なんてものも所詮、ホステスじゃねーか、
と、怒り狂いながら、スターバックスにたむろする
その舞妓の顔をもう一度ぶん殴って、
ほらまるで、
鳳仙花の花が色づくように、
女の顔もやさしい紫になって、
とうとう、スターバックスが燃え落ちるようにして、
炎につつまれたら、きっと、
皆、逃げ惑いながら片っ端からコーヒーを
子供のように行儀悪くこぼして、
泣き叫びながら、
それでもなお、僕は、
長唄のひとつでも、と、彼女の変わりに、
泣き喚く子供たちのために、言うのだろう、
[編集]
朝の遺灰
丘 光平
夜明けの空を 鴉が飛んだ、
昔 巣を飛びだしてからずっとひとり
いためた翼を手当てすることもなく
あほうあほう、あほうあほうと呼ぶのだろう
そしてとおく 星を指さしたまま
白髪になった少年のように
秋が立っていた、赤らむ花と根につながれて
声をあげることもなく燃えるのだろう
きっとそのように なにも身につけずに朝が来るのは
肉を鴉に与えるためか、それとも若さを
秋のほむらにくべるためなのか
あほうあほう、
あほうあほうと 夕焼けいろの鴉の朝が
遺灰のように降っている
[編集]
[次ページ]
投稿する
P[ 1/6 ]
[詩人名や作品名で検索出来ます(2009年9月号)]
▼月刊 未詳24BN一覧▼
2007年4月創刊号
2007年5月第2号
2007年6月第3号
2007年7月第4号
2007年8月第5号
2007年9月第6号2007年10月第7号2007年11月第8号2007年12月第9号2008年1月第10号2008年2月第11号2008年3月第12号2008年4月第13号2008年5月第14号2008年6月第15号2008年7月第16号2008年8月第17号2008年9月第18号2008年10月第19号2008年11月第20号2008年12月第21号2009年1月第22号2009年2月第23号2009年3月第24号2009年4月第25号2009年5月第26号2009年6月第27号2009年7月第28号2009年8月第29号
pic/北城椿貴
[管理]
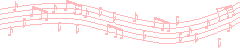



[掲示板ナビ]
☆無料で作成☆
[HP|ブログ|掲示板]
[簡単着せ替えHP]