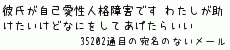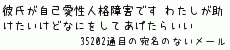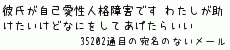投稿日12/31 00:14
「ともかくもあなた任せの年の暮れ」
ジェルガ ヒミカ
−自然の流れで平穏に暮らしていこう−という意味で、「あなた」という単語には世間を取り巻く社会や太陽や大地を含めた自然。または、妻や夫や父や母といった、お世話になった人が浮かんでもくる。
1763年〜1827年没の小林一茶が文政3年にまとめ上げた「おらが春」に収録した句の一つです。一茶は本名を小林弥太郎と言い、苦しい荒奉公の世界で生きる毎日を過ごす中、俳諧の世界に偶然入り込み徐々に頭角を現し当初は「乞食首領一茶」と名乗り。「正風俳諧名家角力組」という相撲でいう番付表では東の最上段の8人目にまで昇りつめるまでになり、後世において日本はもとより世界が知る俳人の一人となった。 そんな彼の生涯は常に不幸が付き纏い家庭には恵まれない終生逆境にあった。
一茶は信州長野の村で百姓の子として生まれ、3歳の時に実の母と死別して8歳の時に継母がやってくるが継母との仲は最悪だった。その事に心痛める日を過ごしていた父は一茶15歳の時、泣く泣く江戸へ荒奉公に出す 。一茶は満足に親の愛を知る事なく宿無しその日暮らしを何年間も続ける事になる。一茶は俳諧の世界に浸かり名が少しづつ売れ出し諸国を旅してまわる日々を過ごすなか、24年ぶりに故郷に戻る。一茶と畑に出ていた父が一茶の目の前で倒れてしまう。父は今でいうチフスの一種にかかり一ヶ月病の床に付した後にこの世を去る事となる。こうして一茶は血の繋がった両親をあっけなく失った。
父を失った一茶は継母との間に12年という長い年月の間、遺産相続で争うハメになる。長い年月を自分の意志ではなく父に言われ自身も泣く泣く故郷を離れてはいた。一茶は本来なら自身が受け継ぐであったモノを主張しているだけの話なのだが、継母に言わせれば長い間家を留守にして、ふいに戻ってきた息子といえども、血の繋がらない息子に夫と長年に渡って蓄えた財産を、むざむざと渡す気には一切ならなかった。だが、一茶が江戸に訴えに出ると言うと継母の態度はコロリと変わり一茶の主張は通る事となった。
一茶は両親を早くに失いその後、継母との長きにわたる確執に疲れてはいなかっただろうか。気の休まる時間は彼にあったのだろうか?一茶はそんな日々を俳句にしたためる事が、自虐的でありながらも、そうした時間が今もこの先も彼を支えていた事が、生涯に渡って2万句を読んだという事から考えても、紛れも無い事実なのかもしれない。
若い時から安らぎや温かな家族だんらんとは程遠い場所に身を置かねばならなかった事が一茶にとって心身の成長に影響を与える事となったのか。自身が身に包まれた事のない家族愛をというモノを徐々に考えられ始め、欲っして、手にしてもよい年齢に十分に達してはいたのだが、実際に一茶が家族というモノを手にするのは、父を失ってから13年後の52歳の時だった。52歳の時に28歳の妻の「きく」を娶った。晩年になってからの初めての結婚に一茶が照れている句が何作か残っている。「五十婿頭をかくす扇かな」その後、一茶は妻との間に3男1女をもうける。長女「さと」の事を唄った俳句が残されているが、いずれも一茶の親馬鹿ぶりが見え隠れしていて、読む程に一茶と娘とのやり取りが目に浮かんできて微笑ましくも思えます。きっと一茶は、やっと手に入れる事の出来た、妻や子に囲まれて過ごす穏やかな日々に今まで感じる事ができなかった幸せに包まれ心から安らげた事でしょう。しかし、どの子も成人する事なく早い子は生まれて一ヶ月、長くて3年とせず一茶や妻の元を離れ、この世を去っていきます。そして愛する妻までもが痛風となってから腎臓を患い37歳という短い人生を終え一茶の元を去らねばならなくなります。その時、妻は2歳になった三男の「金三郎」を残して去らなければいけませんでした。一向に良くなる兆候の見えない妻を看病をする一茶。看病を受けながら床で我が子や夫の顔を見上げ二人の先行きを案ずる妻。何も知らずに無邪気な笑顔を見せる金三郎。一茶や妻の心には、どんよりと厚くどす黒い雲が渦巻き、解決策を見出だせないまま過ごし、ただ弱っていく妻を見ているしか出来ない毎日を一茶はいかに過ごし、妻の死後は一茶はいかにして自分の心にケジメをつける事が出来たのだろう。そんな哀しみに暮れていた一茶の元を三男の金三郎がなんともやりきれない理不尽な原因で母を追うようにして、一茶の元を去っていきます。一茶は一度味わってしまった幸せを再び手にしようと、寂しさを紛らわせようと、翌年に近所の者の紹介により再婚するが、62歳の一茶に38歳の妻は年が離れ過ぎていた為か、二人の生活は半年と持たなかった。その2年後に一茶は32歳年下の「やを」と結婚する。やをは2歳になる子を連れていたが、やを自身が一茶の子を産む事を願っていたというところから、またもや年齢は離れていたが、二人の夫婦仲は良かったように思える。一茶は64歳にして、今までに何度となく指の隙間から逃げるようにして去っていった幸せをやっと握りしめ安住の地を得る事となったのだった。けれどもその幸せも今までの一茶の人生らしくもあり、長くは続かなかった。やをと結婚したその1年後。大火で母屋を失い、焼け残った土蔵での生活を余儀なくされた一茶は、その年の11月にこの世を去った。そして皮肉にも一茶がこの世を去った翌年の4月に、やをと一茶の間に「やた」が生まれた。やたは一茶の血脈を46歳で没するまでの間、後世に伝えた。
一茶は幼少期から晩年に渡るまでに続いた家庭的な不幸が彼の作風に多大な影響を与え、一茶が作り出すその句は多くが社会的弱者や子供。鳥や小さな獣へ暖かい眼差しを向けて創作されている。
一茶の人生は壮絶だ。様々な悲運が連なって重なり合い、どこを切って開いてみても、次の悲劇までもが顔を覗かせているようで、目を覆いたくなる。しかしそんなものは一茶が生きた時代では、珍しくないようだ。薬も無く、身内が病に倒れても手術を受ける事すらないままにこの世を去るのも、口減らしの為に故郷を離れ奉公に出されるのも、継母と確執が生まれ、肩身の狭い思いをするのも、当たり前の時代であった。一茶は身に迫り来る様々な悲劇から幕を下ろす事も急に舞台を降りる事なく己の人生を貫いた。
一茶の生きた時代は交通網も今のように整備されておらず、現代よりも酷い縦割り格差に、各地に点在したであろう命の取り合いが日常茶飯事の無法地帯。果たして、21世紀を生きる現代人の我々が一茶の生きた時代に生まれ変わったとしたら、どれだけの人が自分を見失う事なく、前向きに生きる事が出来るだろう。一茶の人生を体験するハメになった時、どれだけの人間が一茶のように生涯を通じて自暴自棄になる事なく、ささやかな生き甲斐だけを楽しみに人生をおくる事が出来るだろう。
昨今の他人を思いやらないニュースを読んでいると、人は新たなる利便性を追求し、手にする度、引き換えとして我慢が効かなくなり、心が弱くなっているのかもしれない。けれども、そんな凄惨な事件は昔からあったのだろうが、現代はメディアの力によって今起きてる事件は現代ではスタンダードな事件として伝えられ始めているような気がします。
あの時代において、一茶本人は個人としても俳人としても特別な存在であった訳ではないと本人は思っているのではないか。同時に今を生きる私達も特別な存在ではないと思う人が大半だが、現代は誰もが後ろを向いて、頭まで垂れて今を生きている。そんな世の中だからこそ、どこかで人が前を向いて、たゆまず歩む姿を見ると他者は勝手に自分にないモノを感じとり感銘を受けるものである。それが結果として後世に遺る事もあるのだ。
私達は何も一茶や著名人のように、多くの人の心に遺らなくていい。2009年は自分を大事に想ってくれている人。自分が大事に想っている人に誇れる自分でありたい。
編集
△このコラムのTOPへ戻る
▲コミュに民のトップへ
小瓶に手紙を入れて海に流すようなコミュニティ