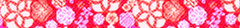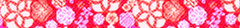
投稿する
[前ページ] [次ページ]

終りは終りのなかで果てなく続く
及川三貴
強い風で海から潮があがる
輪郭を弱めて 遠い
少しよろめく程の 嘘がいい
丁寧に紙を貼る 名前を無くした
もう誰も知らない信仰
角が取れた河口の石は
死の形をしている
記憶は疲れた顔をしている
陽を隠した掌の陰
微笑んだ口許は
私を何時までも苦しめる
あれは何年そこにいる
錆びの苦しみに 身体を晒して
内側からすこしづつ溢れてくる水だ
届かない
ここが中心
願望の先にある時間
想像する
間違いだった
ここが中心
嘲笑の為の
美しい音色
[編集]
夏風邪
泉ムジ
こんな初夏の日に、風邪なんかひいているのは、恥ずべきことである。咳をした拍子、凡庸な不満が爪先に転がり、「蹴飛ばしちまえ」と唆す。ああ恥ずかしい。顔を伏せたまま、誰にも見られぬうちにそっと、そいつを道端の側溝に滑らせ、もみ消す。どれほど切実だとして、凡庸な不満ごときに、私の生活を脅かす権利があるだろうか。いや、ない。だから風邪薬を買わねばならない。それもとびきり効くやつを。肩をすぼめて大通りを渡り、素早く裏道へ潜り、狭いコンクリートの階段で地下におりる。どん詰まりにあるマンホールの蓋を強く2、3度ノックすると、黒人の前歯がぎらぎらきらめく。「よお兄弟。新しい宗教は要らないか?」要らぬ。私が欲しいのは、風邪薬だ。下水道の暗がりに、断固として言い放つ。途端、誰もこたえる者がなくなり、くすくす笑う声の反響が、私の心臓を刺す。血の味にむせ、切実さを増した咳が転がり落ち、いっそう笑い声の反響が大きくなる。ずぶずぶと刺す。「蹴飛ばせ! 蹴飛ばせ!」そこかしこに咳をふり撒きながら、私は走った。走ればまた息が荒れ、いよいよ破れた心臓から情けない音がもれ始めた。
[編集]
夜に死なない
黒木みーあ
ないていた。
どこか遠くで、日を捨てる音がする。昨日と、今日と、明日と。夜にさえ、抱かれない。わたしの、帰る道。立ち並ぶ家に人は居るのに、話声ひとつきこえない。石壁に反響する歩く音は、乾いた鼓膜を少しずつ圧迫していく。二つ目の曲がり角、ないていた。夜に刺さる声、二階建ての空き家。そのてっぺんできいきいと、風見鶏がないていた。それをいつも、いつもいつもどうにかしてやりたいと、思っていた。わたし、わたしは、たぶんわたしが思うよりもおかしくなっていたのかもしれない。頭が、ひどく痛かった。その日は、男のモノをくわえているのがいつもよりも苦痛で、とにかく頭が、痛かった。
あの、吐いても、いいですか、
言葉よりも先に、モノが出た。男のモノを噛み砕く、一歩手前で。薬が欲しかった。なんでもかまわない。今日に限って忘れてしまっていた。頭が痛い。男の情けない顔、わたしはどんな、顔をしていたのか。不意に笑いそうになる。おかしかった。とにかく、とにかく。何も考えずに飛び出した。小さい頃は全力疾走とかしょっちゅうで、でもやっぱりあの頃のようにはいかない。走りはじめてすぐに、胸が痛くなった。それに同調するように頭の痛みが激しくなる、ずきずき、ずきずき、暗い、路地裏。明るすぎた場所からの影響でうまく前が見えない。生ごみの臭いがする。寒かった。一瞬、裸かと思ったらわたしは服を着ていた。おかしかった。電話が鳴る。半狂乱の店主から、半狂乱な声で、どうしたんだと。どうしたんだと、わたし。いやどうもしていない。わたし。誰にも会いたくなかった、もう、思いつく限りの罵声を浴びせて、電話を切った。
歩きながら、わたしは死んでいた。今までと同じように、ひとりずつ、わたしが死んでいった。
なかなか治まらない胸の動悸と頭痛で、死期が早まるように、どんどん、どんどん死んでいった。一体、後何人のわたしが残っているんだろう。急に走るものじゃない。昔誰かに言われたことがあった。親だったか、愛そうとした人か、遠い昔ほど、よく覚えていた。気付けば足も痛い。走れるような靴ではなかった。路地裏からいつもの道に出た。わたしは真っ黒になってしまったんじゃないか、そんな気がしていたが、ガラスに写るわたしはいつものわたしだった。眩しい。この街のネオンが心底嫌いなんだと、思った。
少ししてまた、電話が鳴った。友人。という文字が画面の中で点滅している。とらなかった。捨てた。わたしには友人はいない。吐き出す息と一緒に声に出す。いたことさえない。今すぐ、飛び降りてしまいたかった。もう、どこか高いところから、気絶しておしまい。おはよう地獄。きっと今だって、頭が割れているに違いない。でもほんとうは死にたくないと、思ってる。わたし、わたしはわがまま。わがままな子だと、小さい頃から親が言い続けたように、わたしはわがままだった。わがままじゃないといい続けたわたしは、たぶん、一番はじめに死んでいた。
自然と、帰路についていた。昨日と同じ帰り道には、昨日と同じように少しずつ明かりが失われていく。時間がいつもより早くても、夜に変わりはなかった。外灯はくたびれ果てて、出迎えることは決してしない。通る度、夜の温度が濃くなっていくような、そんな感覚を抱いていた。どこの家も真っ暗で、わたしも、同じように真っ暗だった。誰も居ない。居ない。帰っても、わたしはそこに居ないし、ここにも、居ない。
かなしい声がきこえる。わたしの、風見鶏の、声。ないていた。くたびれた外灯の端に建つ空き家の、漆黒の闇のてっぺんで、風の吹く度ないている。わたしは後何人、残っているんだろう。何度も思いながら、空き家の前で立ち止まった。もうきっとおかしくなっていた、頭が、痛かったし、無性に笑いたかった。何も飲んでいないから、口が酸っぱい。あんなモノ、噛み砕いてやればよかった。一瞬、そう思って、でも噛まなくてよかったんだと、思いなおした。
ないている。いつまでも、風見鶏が、誰もいない夜に向かって。ないている。今、どんな顔をしているんだろう。朝の雄々しい姿を見ないままでいた。でもそれでよかったのかもしれない。誰も居ない家のてっぺんからは、きっと、かなしい景色しか見えないでしょう?うずくまる、わたしの背中を預ける夜が寒いのは、昨日も、一昨日も、ずっと、ずっと同じ。帰りたかった。どこかに。わたしの居るどこかに。胸の動悸が少しずつ落ち着いていく。ないている。ずっと。ないている。わたし、わたし、わた、し、ばいばい。小さく叫んだ。外灯がじりじりと唸っている。その音よりもずっと小さく、けれど叫んだ。おもいきり。ないている。ずっと、ずっと。ばいばい。
立ち上がる。頭はどうせ割れていた。今何人目かはもう、わからなかった。ないている。わたし、もう、ないていない。またひとり、死んでいった。夜の底の、底の、底。上を見上げても、何も無い。そんなことずっと前から知っていた。星よりも多い、わたしの死体は星よりも弱く、瞬きもしないこと。一体、夜はどこまで、高くなるのか。長い間を、宛てもなくないている。目を閉じていても、開けていても、わたしが確かに、そこに、死んでいる。
[編集]
肺に混じる雑音
フユキヱリカ
[hi−fi]
咳をしたあと
ひゅう、ひぅ と、
咽喉が鳴るんだと思った
きみは 背を震わせていたんだ
いつもそうやって
シーツのなかでつま先だけが冷えるから
それから眠れないでいた
あの夜、窓を叩いた枝が
葉を繁らすころ
皮膚の匂いが濃くなるのを嫌った
僅か残すばかりの線を
知るのを急ぐように
の、を急ぐように
原音を忠実に再生する
私を見てわらう
hi−fi
噛んだ唇をわらっても
その目を睨み返したことも
てのひらをぎゅっと握り締めたことも
おとなになればわすれるのに、ね
また泣いていたの?
そうじゃない
きみにやさしいことばをあげたいんだ
きっと うまくいく と
つぶやいて
明日を待って眠る
ただ眩しくて見えない空、
青空のファルセット
[振動数]
震わす唇のクラップ
コホン、と 吐き出した息
真っ白いコンクリートの壁を
叩きつけるよう何度でもハウリングするたび
君の肋骨が持ち上がる
通過する雨を待つ花のようだ
祈るように ただ待つだけ
じっと暗雲を睨んで
あおいあおい血管に水滴が落ちる
てのひらを強く握り締めても振動数がたりない
味のないスプーンを君がおいしいと頬笑む
膝の上に涙を包んで
わたしはそっと席を立つ
細長いチューブに成ってしまう君が
わたしの名前をもう
覚えることはなくても
その眼で見ていてほしいの
*
[編集]
[*前] [次#]
投稿する
P[ 2/4 ]
[戻る]
[掲示板ナビ]
☆無料で作成☆
[HP|ブログ|掲示板]
[簡単着せ替えHP]