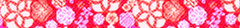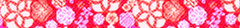
投稿する
[前ページ] [次ページ]

誰も嗅いだ事のないいかがわしい臭い
ホロウ
ふたつの言葉が死んで
ひとつのフレーズが残った
俺はそれを際限なく殴り
本物の血が流れてくるまで待った
稲妻は脳髄を
喰らいつくすように走る
傷みとも呼べそうな恍惚に
振り回されながら俺はキーボードを叩き続ける
ゆがんだ直線の道路
狂った坊主の読経
陰茎をおっ立てた牧師
日向で茶を啜るヴゥードウー
銀色の針が降り注ぐみたいな夜明けに
お前の一番汚れた部分を晒せよ
冷えたコンクリートの森で悟りを手に入れたいなら
生肉を屠る感触はブレインのコントロールで
お前は極彩色の夢を見たがる
手っ取り早く気持ちよくなりたがる
濡れるために必要なものがスタンダードな妄想だって言うんなら
漏らしたものはヴィトンのバッグにでも塗りつけておくがいいさ
どんなに空が晴れても
光の当たることのないビルの物陰で
ひとりの清掃人が売春婦の死体を解体している
それは仕事だ
秘密裏に処理せよと雇い主から命ぜられた
年老いた痩せぎすの小男には判っていた
この女は死んだが俺はまだ生きなくちゃならない
血塗れのミンクからはち切れそうな財布を取り出して自分のポケットに入れた
どこかの暢気なオフィスの窓から
オール・ニード・イズ・ラブが流れていた
小男はミック・ジャガーとそんなに歳が違わなかった
その歌を聴くと
いつでもミックの声を探してしまう癖があった
さらに三つの言葉が死んで
俺はひとつのフレーズを反復する
そして新しいフレーズが駆けだすのを眺める
植物の交配を試しているみたいなスタンスでそうしている
植物の交配を試してみたことなんか一度だってないけれど
お前はいつだって初めから
言葉というものを捨てている
肉体以上に語るものはこの世にないのだと
そう信じているみたいに見える
だからそんな風に解体されちまうんだ
祈りすら捧げられることもなしに
血と
どこかひやりとした内臓の臭いに
小男はしわだらけの顔をしかめた
暑くなる前でよかった
暑くなる前でよかったと
清掃中の看板で閉鎖された路地裏で空を見上げる
建造物の間で見える一筋の空は
神が滑るための道のように思える
男の首には冷汗ともただの汗ともつかないものが
世界を確かめるみたいにゆっくりと滑り落ちる
あらゆる文脈がストップして
俺はキーボードに指先を預けたまま画面を眺めている
昨日よりはましな気温なので
待っていることは別に苦痛じゃない
男は妙にそうしたことに手慣れていた
牛か豚を捌くみたいにたんたんと作業を進めていった
きれいな身体してやがるな
と
男は思った
その仕事についてまだ間がなかったのかもしれなかった
そしてそのキャリアは永遠に更新されることはない
排水溝に血が流れていた
ここらあたりの排水溝にはきちんとした蓋がついていたので
そこに流れているものを誰かが咎める心配はなかった
動かなくなった所から
ふたたび俺は書き始める
逃げた熱がまた指先を騒がせて
閉じかけた目がまた次の展開を欲しがる
90分で女の身体をそこからすっかり消してしまうと
路面を掃除して消臭剤を振りまいた
たいていの臭いは消えてしまう強力なやつで
そこらですぐに手に入るというようなものではなかった
雇い主がどんなルートでそんなものを手に入れているのか男には疑問だった
が
それについてはなにも聞かないことにした
多分聞かない方がいいことに違いないのだ
男は路面を細かくチェックして
やり残したことはないと結論した
仕事道具をコンテナに詰め込んで
その上に座って煙草を吸った
仕事を早く済ませ過ぎたことに気がついたのだ
一服したら専用のごみ捨て場に行って
でかいカゴの中にこいつを放りこんでしまえばいい
財布の中にはいくら入っているだろう
煙を吐きだしながら男は空を見上げた
そこを通過する神の姿は見当たらなかった
俺にはビニール袋の中の女の瞳が見える
その瞳がまだ生きていて
どんなものを見つめているのか知ることが出来る
彼女と言葉を交わすよりもはっきりと確かに
そして俺は新しいフレーズに手をつける
誰も嗅いだ事のないいかがわしい臭いが
そこに漂っているのならそれでいいさ
[編集]
落日/日々、忘れていく
えあ
薄く開かれた
キッチンの真新しいに
わたしは指を押し付ける
きらきらと
埃が光を透けて
背中のむこうを越していく
手の届かないところに
静止した
なにももらさずにいるから
どうか
伴れていって
まだ沈黙している家具の
その隙間に
押し込められたからだ
ほどけていく落日が
隠してはくれない
風はかんたんに空白をみつける
いつからか熱をもついきものになってしまったから
合図があれば
やわらかくなってしまう
丁度いいおおきさになれたと
笑ってくれたひとは
今はもう遠すぎて
うつくしく、磨かれすぎた床に
拒絶され
もうできることはなにもないよと
歌ってくれたひとたち
をおもいだす
呼び鈴がなる
ただただひれふして
冷たく他人になってゆくのを黙ってみている
買ってきたビタミンカラーの野菜は
もうきれいだから
そのままにする
適当な所で鮮度を保っていて
荒れた手で
口に運ぶことのないように
こごえた通路のさきでは
またはひらかない扉が
汚れるのをまっている
だけれどいつか
生活的に濡れたゆびさきを
だれかの愛しいが
あたためてゆく
そうして
壊れるから美しいものを
留める指を
ほほえんだりせずに
やさしくこわしていきたい
[編集]
春のまぼろし
黒木みーあ
のそり。枝垂れすぎた桜が、穴開きブロック塀の上を跨ぐようにして、地面に口づけをしている。
ような格好で、あたしの方にお辞儀をしている。薄桃色の、明るい、花色。雨上がりの陽に触れてそれは、どことなく艶めいて見える。
きっとまだ、誰にも触れらていないんだろう。そう思ってあたしはそのさきっちょをぽきり、と、へし折って手に取ってみた。(( ちく、と小枝が刺さる。僅かな、罪悪感。人並みの。風が、腹部の方から、突然やってきてあたしの、鼻先を突き抜けていく。
吸い込む空気に、香る。中へ、中へ中へと、満ちて、いくように、春。
光合成。草木の、一年ぶりの、でもとても懐かしい匂い。
あたしは道を行く。ごーすとりーと。無駄に広い、道幅。
並ぶ家々には、剪定されていないままのレッドロビンが、四方八方に手を伸ばせる限りに伸ばしたと、言わんばかりで、(( 頭の、隅っこの方では、"垣根の定番!成長の早いレッドロビン!"と、いなくなった父が、勝手に補足を始めている。
道なりに、角を曲がる。その右手やや前方、片手を高らかに空に向けているかのような、痩せ細った梅の木が一本、
空き家の庭で、今にも死にそうに、生きているのが、見えた。
*
背中を、蹴られたことが、あるのです。誰とは言わず、誰にでも。
そんな時、いつも、存在しない理由は、追撃のように背中を貫通して押し寄せてくるので、わたしのからだは、それらに耐えうる強度を手にした驚くほどタフな、
からだ、で、あれたなら、嘘、ばかり生まれることも、なかった。はず、でした。
お医者さん、が、言うにはどうも、わたしの、わたしが、わたしであること、にも、原因が、あるらしく、て、(( こ、の、ヤブ!とかなんとか、父がまた、頭の中で叫んでいます。それはいつも遠い、感覚に似ていて、
母は、きっとそこには、いません。たぶん家にも、いません。
*
暗、転。陽が陰ると、なぜだか世界は暗くなるようで、そんな時はいつも、瞳、の、奥の方、くすぶっていたあたしが顔を出す。おはよう。って、角を曲がった先で、猫。
今日は、晴れ、時々曇りみたいだね。そんな風にほんの、少しだけ、互いに半身を並べて、しばらくの間並行に、歩いていく。
(( 意識、しないように、横目で。きっと猫もあたしを、意識、しているんだ。そのうちに、突き当たる。次の角。右か、左。一瞬、立ち止まった。猫も、あたしも。
*
先天性の、ものでしょうと、ため息混じりでお医者さんが言うのです、から、から、
今のわたしは、必ずしもわたしのせいでは、なくて、ねえお父さん、見てください。
(( 聞こえているのなら。今日も、ああこんなにも陽は、あたた、かいのです。もう、春です。風の、匂いに溺れてしまいそうで、今年も、またからだの中を春が巡って、いくから、
(( 震えて、しまうわたしの、癖。わたしの、わたしたちの真昼を、言葉にはなれない言葉の光で、満たしていく、みたいに薄明るく眩しくてまだ、その陰りの反動が、どうしても怖いの、です。
*
互いに、あたしはお尻を、猫はキュートな尻尾を、背中で見送り合って、別々の道を行く。
すぐにまた陽が射してきた。それと同時に、肌寒い風が急に勢いをなくして、やさしく頬を寄せてくる。
またひとつ空き家を通過する。古い、平屋建て。誰を迎え入れるわけでもなく、クレマチスが花を咲かせている。ここにも、春。旅人の喜び。
という花言葉を思い出す。(( 声色の、高い、母の声がする。父のいない、まどろみの中。春の、陽だまりの中で、聞こえる。母の、声はいつだって、いつだって笑っていた。
確かなもの。陽だまりの中では、母の声、は、
*
―――お腹が空いたなら、道に生えている花を食べます。
意外に美味しい、花の蜜。は、ささやかな、生きている喜びを、晴れている時にだけ、時々、くれたりもしました。
幼い頃の、帰り道、暮れていくのは日だけでは、なくて、焼けていく空には、わたしの亡霊が束になって重なって、いつも一緒に、燃えていました。
散りじりに、裂けて消えていく雲の、姿。巡る、血の色。人であるように、わたしも、ほんとうは安心したかった。
*
遠くへ、歩いていたはずの、あたしは何故か、さっき歩いてきた道を、また歩いている。角を曲がる。
空き家の庭の中、梅の木が立っている。死にそうな、あたしに負けないくらい、細い、からだ。
指先に紅色の、春を、僅かに巡らせている。脈々と、脈々と。そんな風にしてあたしは道を、戻っている。また、戻って、いる。
(( 立ち止まる。さきっぽの折れた、枝垂れた桜。しゃがみ込んだ細い、後姿が目の前で、静止する。止まったように、血が、引いていくのがわかった。頭から突然に、よろめく。手をかける、ものがない。
桜の淡い、花色に似た、民族刺繍。ホルターネックのサロペット。
もうひとりの、あたしの、後姿。
*
目の前で、立ち上がる。桜の、小枝を手に、持ったまま。水溜りの中へ、飛び込んだ陽が風にゆられて、あたしの瞳へ、跳ねてくる。眩しい。
消えていく、もうひとりの、あたし、の、後ろ姿、消えていく。目を、閉じる。
今にも、零れてしまいそうな陽だまりの、中で、
(( ――風の匂い。花を食む感触。
目を見開いた、
ゆびさき、ふるえながらわたしは、
夕空に燃えるわたしの亡霊を、
見つめて、いる。
[編集]
雨をスケッチする
ラムネ工場
無限小と無限大とよばれる番いがちょうちょを啄ばんでいる
雨上がりはまだ地平のむこうにひそんでいる
くちばしにこびりついた燐粉が死んでしまった!を水煙で香る
雨だれの音楽葬でさようならする
16ビートでさようなら
ディスプレイされる剥製のコーラに
くぎ付けられたストローは
かつて真白で
真直ぐだった
そういった足をした老女は
泥の溜まりを破壊している
ゆらゆらとないがしろにされながら
着地した傘は仰向け
雨水をさえぎるどころか
雨量を加速させる傘下
オナジマイマイの甲殻の渦は
巻き戻した日々の数と等しい
あまり雨天をリフレインすると
触覚のさきから樹木になってしまうので
雨季いがいは外国になりをひそめている
電線をつなわたりするのが
さいきん幽霊のあいだではやっている
霧雨に目をこらすと
ショートした電光に照らされた
彼らが墜落したりする
と猫がおしえてくれた
銀色の目をぎらぎら光らせて
画材屋の常連客で
白の絵の具をガロン単位で購入するものがいて
なぜそんなに白色がご入り用ですかとたずねると
雨をスケッチしていますのでと答えた
雨は白いですかとたずねると
黙ってうつむいてしまう
雨水をそっとパレットにうつして
画架にかけた白布にぶちまける
灰色の筋を残したのは
あるいは
もっとも率直であろうとすれば
感情で
それを修正するために白をつかう
虹はどうですか?とたずねると
そんなものはみたことがないと答えた
[編集]
庭
島田さえこ
掃除婦は
寂しくなんてありません
一面に散らかった紙吹雪の
飛んでいたところは知りません
薄暗いその部屋は
気怠さの跡だけがだらしなく
毛羽立った瑕だらけの床に
ぽつりとこぼれた濁りなんて
よくよく見ないうちにひと拭いすれば
息の詰まるような歓びも
ピリピリとした悲しみも
無かったようにたちまち消える
だからたぶん
わたしたちが生まれたのは
お祭りが終わった次の朝
秋のはじまりに
友達と友達と
三人で抱き合って風を嗅ぎました
蝉の抜け殻が
重そうに揺れるあの庭木
病んだ人が脱走して
みんな白い服を着て
笑いながら探していました
何もかもおだやかだったのです
本当はやりたかったなんて
忘れてもいいくらいに
花嫁の色は
よれて黄色ばんだ白なんです
前立腺のことは
後回しでいいんです
そっと息を殺し
黒々と欲望の字を書いて
二つのお尻が
浮かび上がるのを
うっとりと待てばよかった
音楽を聴いて
街を彷徨って
深夜のテレビで顔を焼いて
性病の名前は言えないのに
何も残せないことが
震えるほど恐ろしくて
あの頃の
わたしたちは
正気のまま
全てを壊してしまう
神様のこども
庭にはたぶんベンチ
色褪せた思い出には
ひとさじの甘い不安
[編集]
[*前] [次#]
投稿する
P[ 2/4 ]
[戻る]
[掲示板ナビ]
☆無料で作成☆
[HP|ブログ|掲示板]
[簡単着せ替えHP]